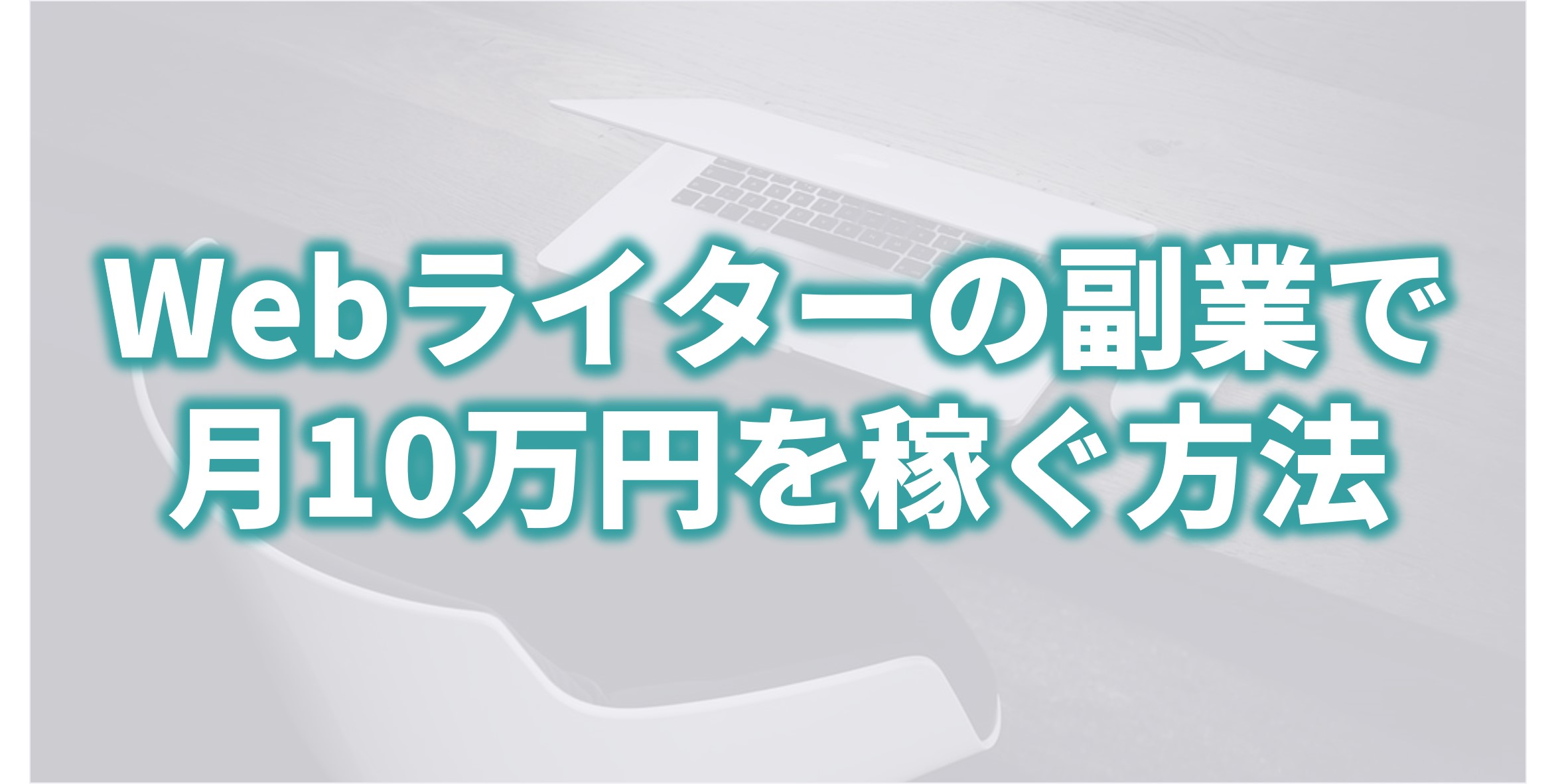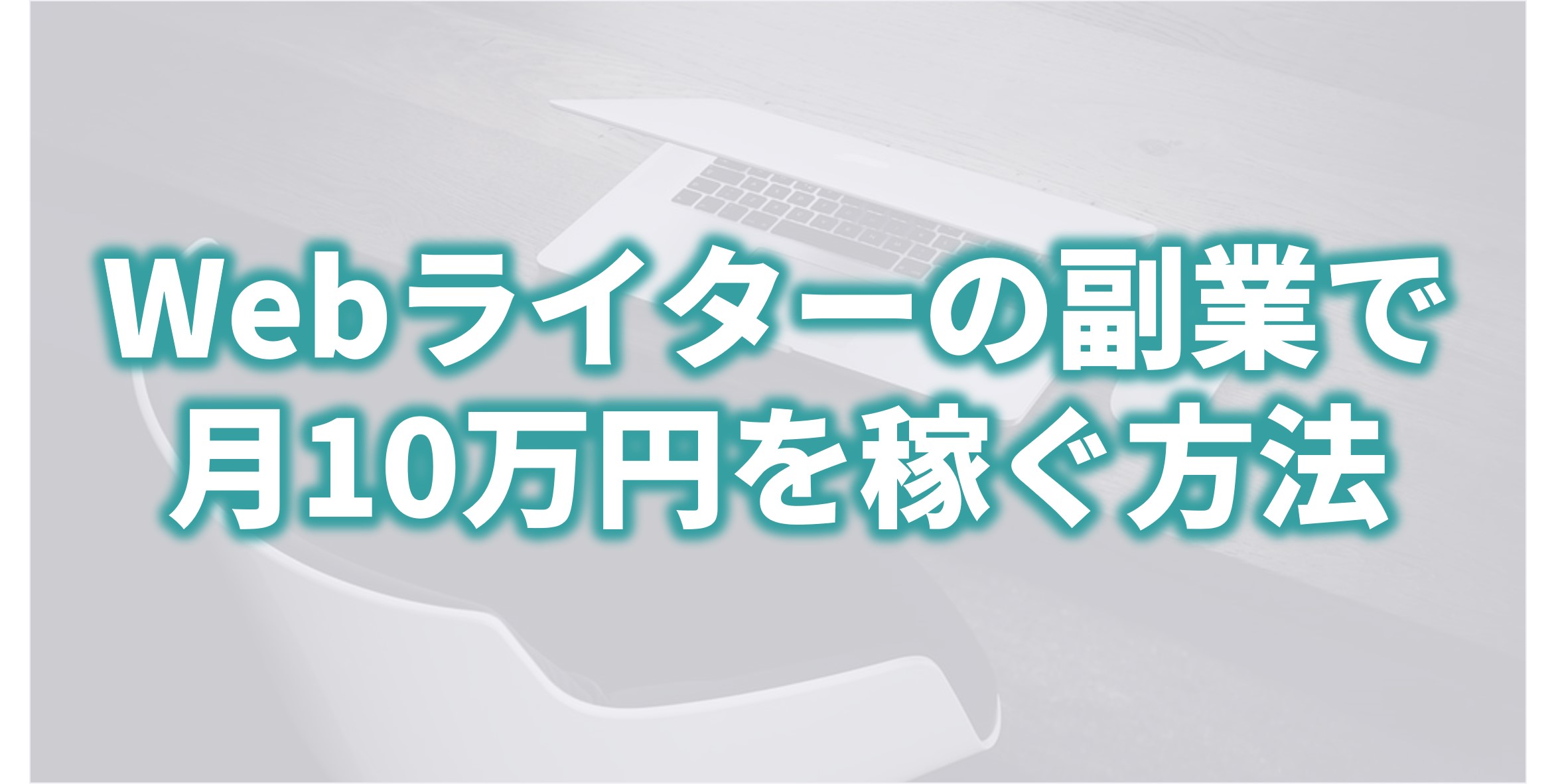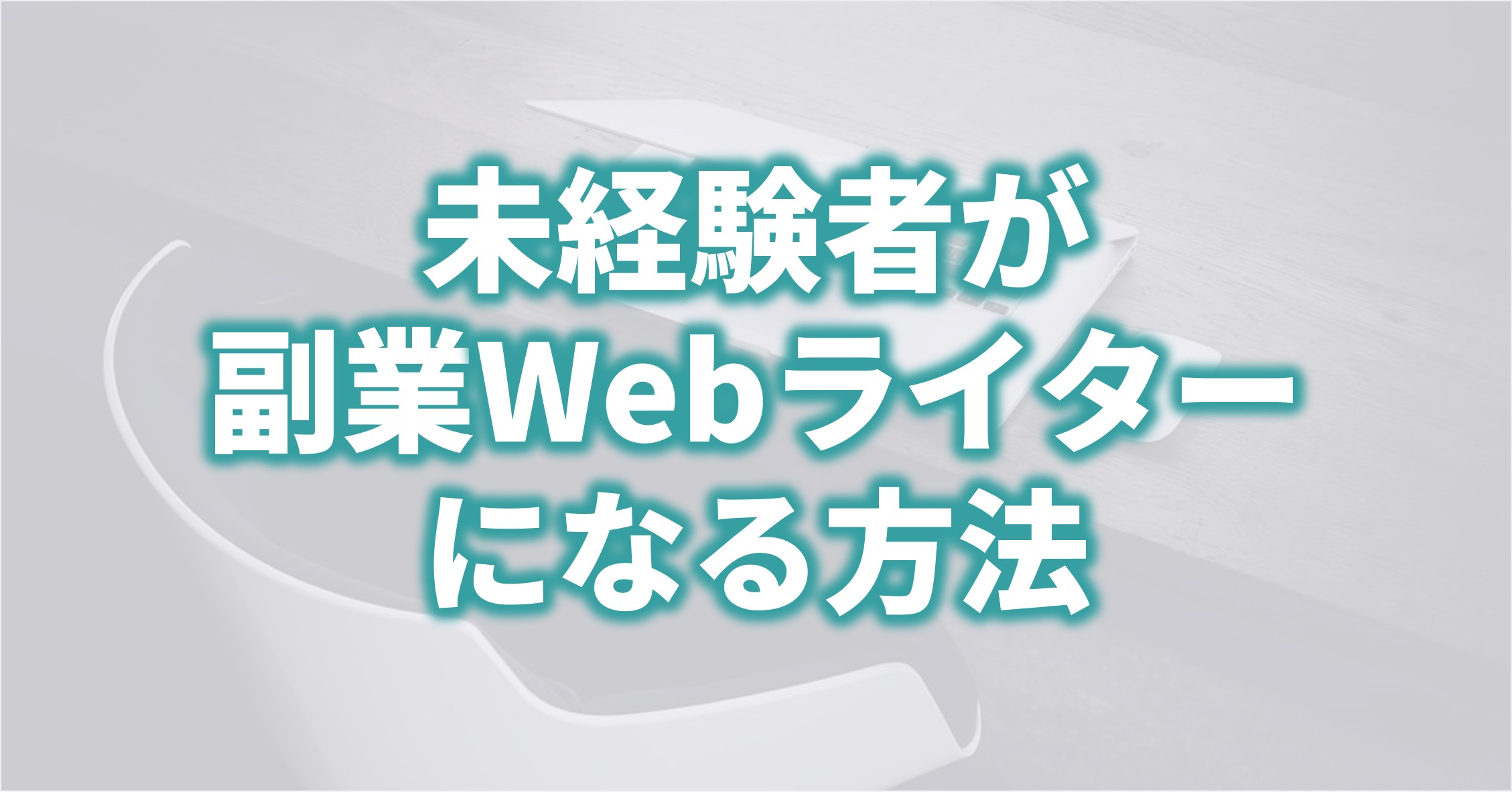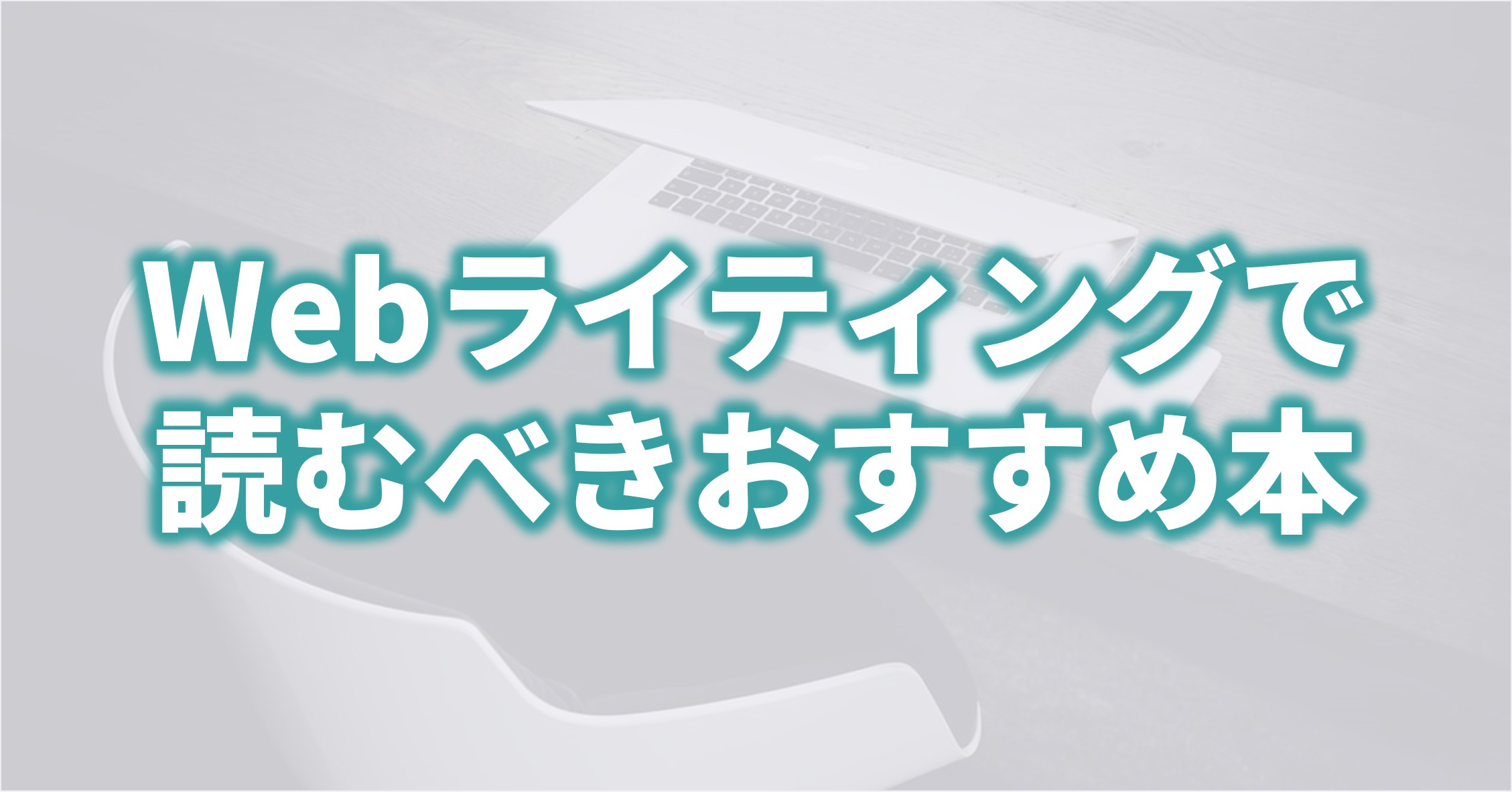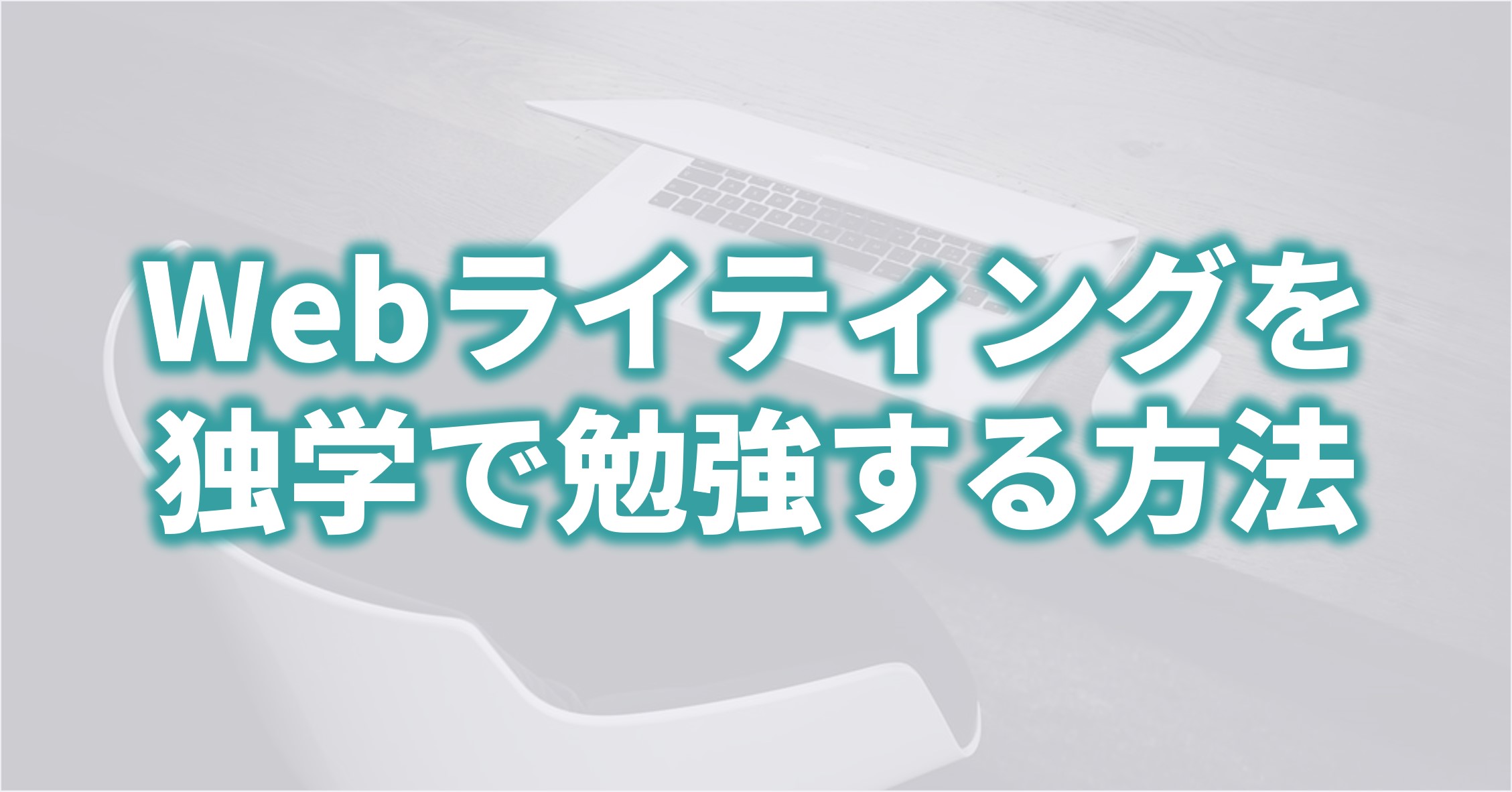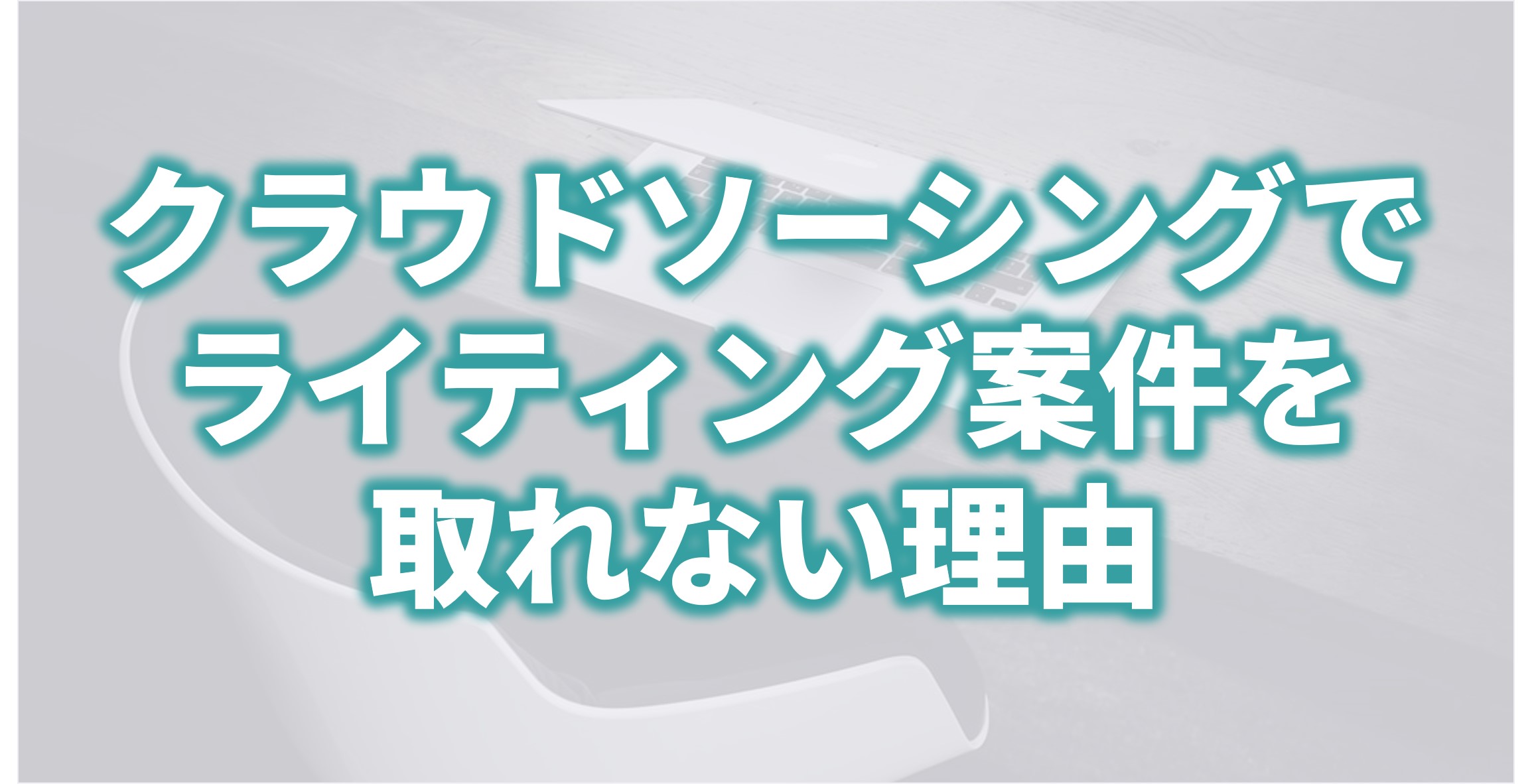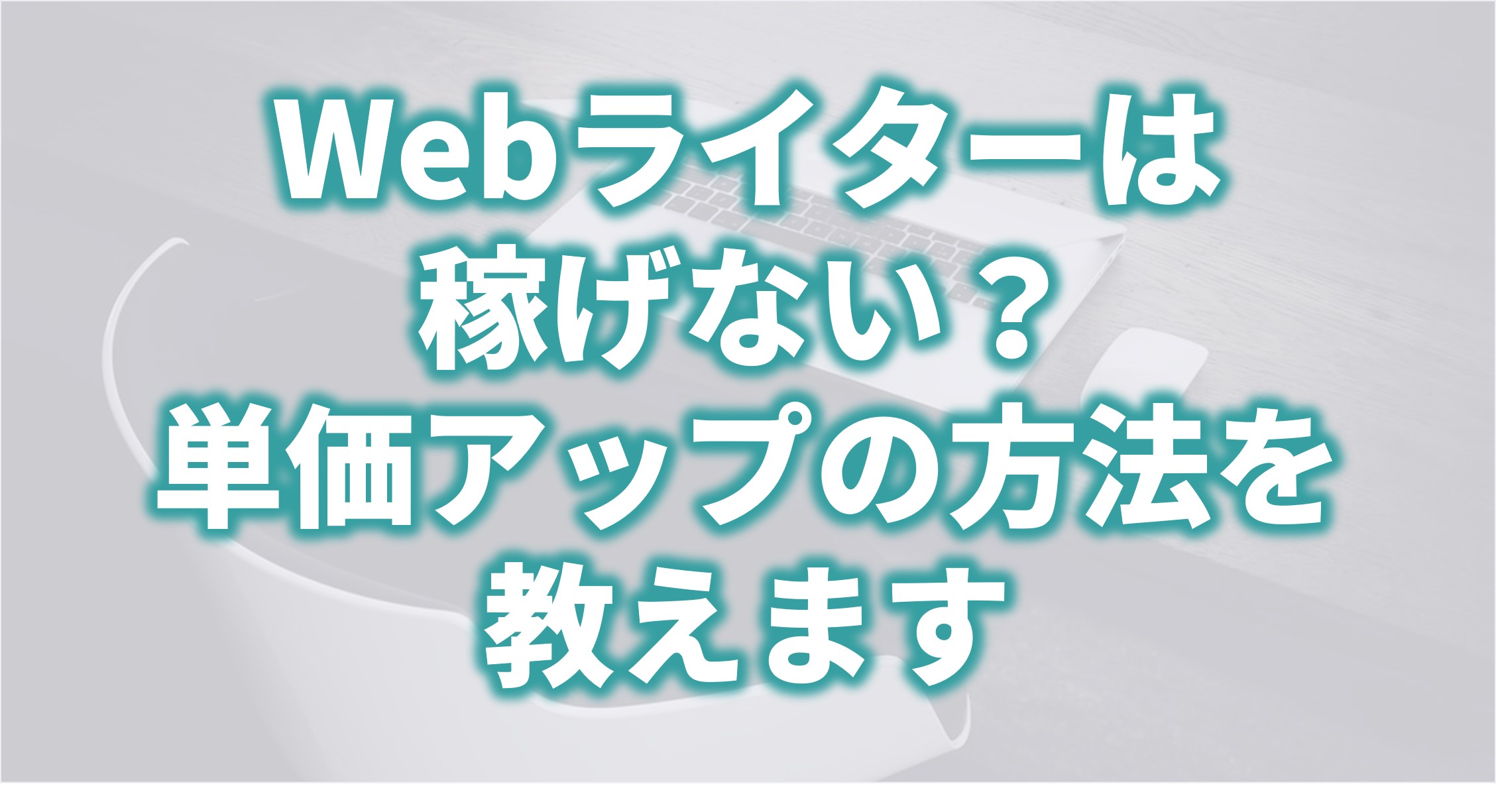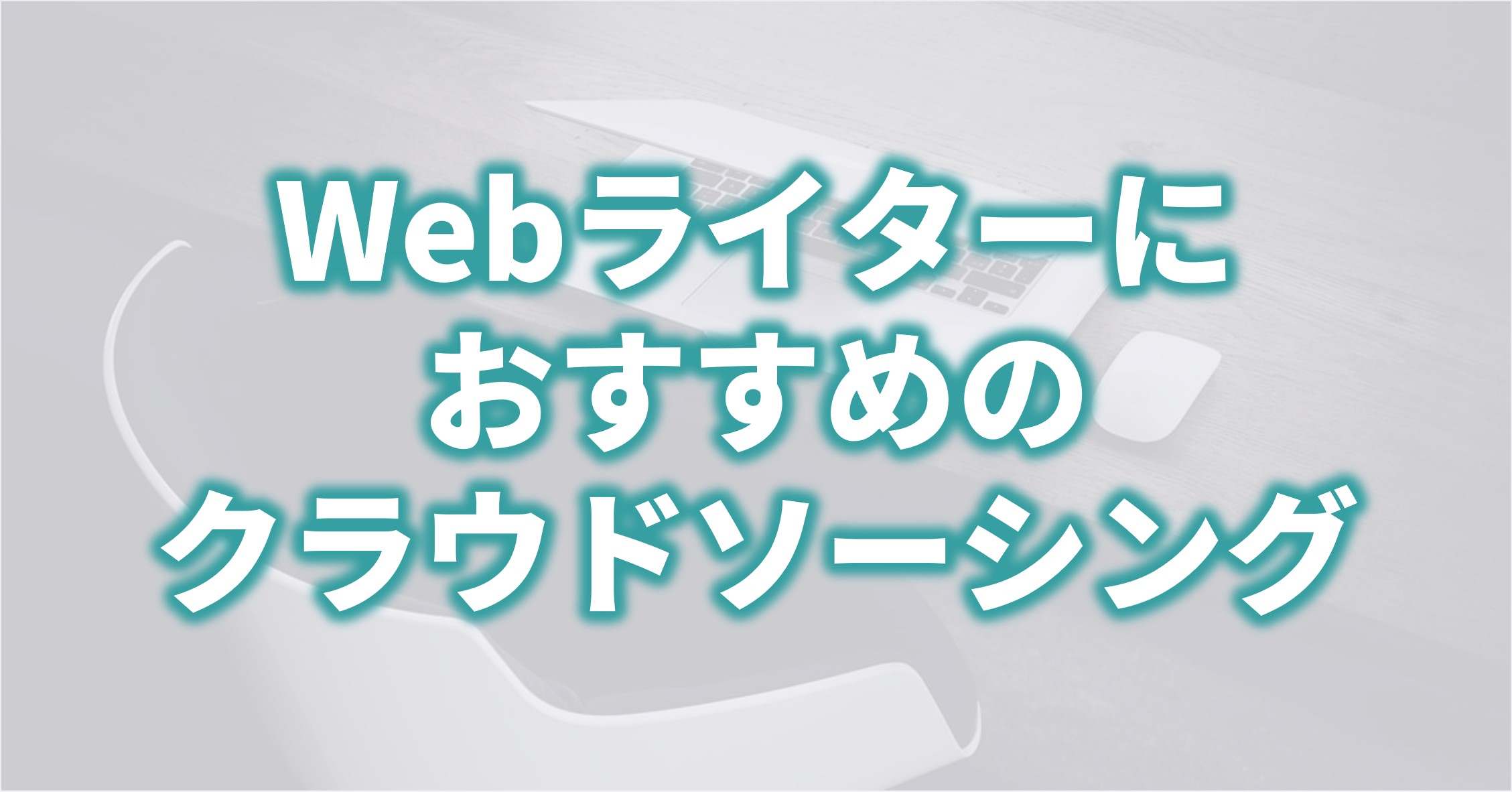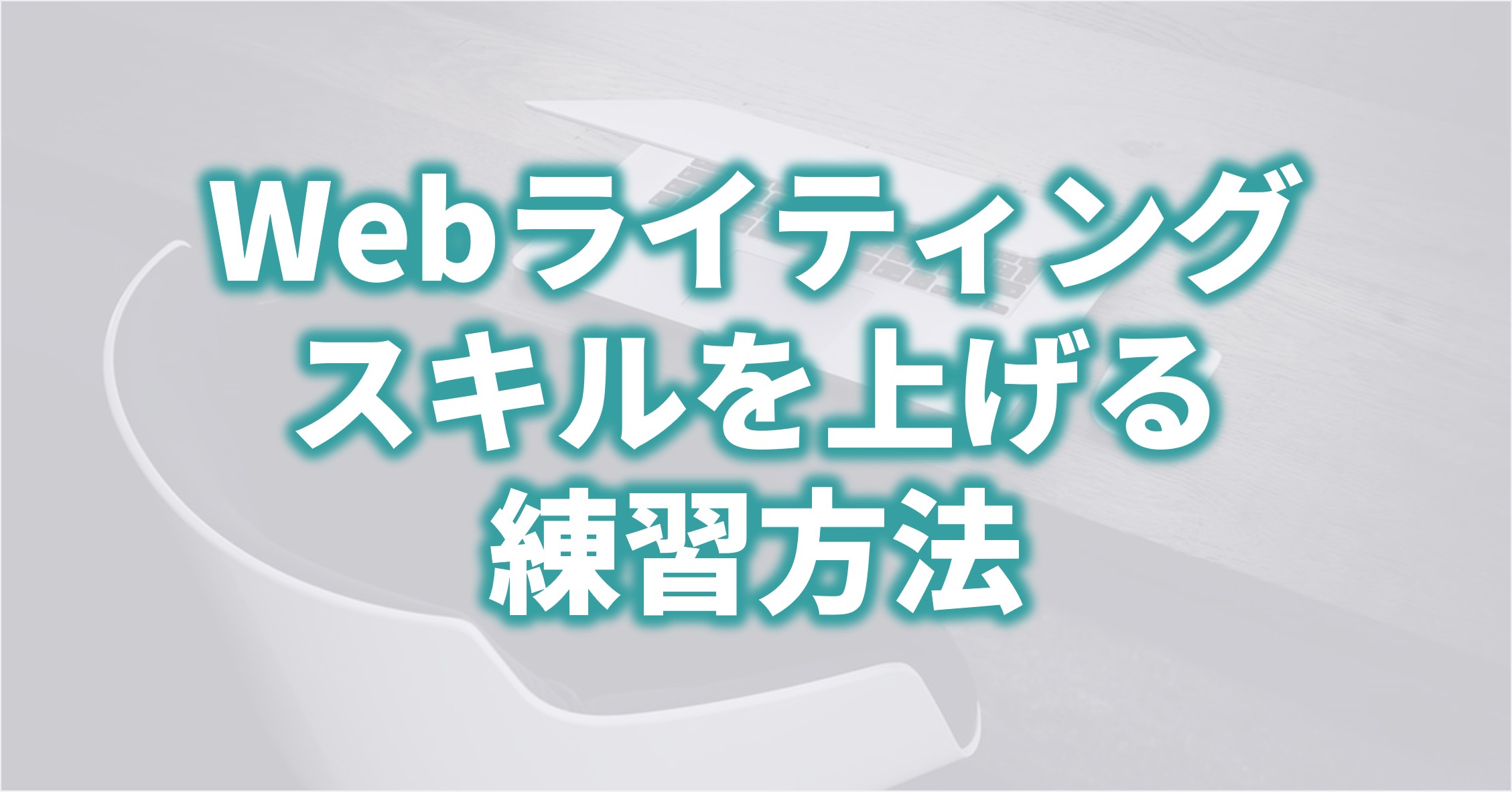ふるや
ふるやライティングがうまくなるためには、チェックリストを作ってセルフチェックするのがおすすめです。
この記事では、ライティングをするときのコツとして活用できるように、外注向けに作っているマニュアルを一部公開しながらポイントを解説していきます。
この記事に書いたことを実行するだけでも、クライアントに納品する記事の品質は劇的によくなります。
Webライターとしての信頼性を高めるためにも、必ず取り入れてみましょう。
文章に関するルール
文章に関するルールの中で、一般的によく指摘される内容を挙げました。
数字やアルファベットは半角にする
数字やアルファベットは、半角で表現した方が綺麗に表示されます。(と思っています)
行政文書などでは、全角の数字を使うケースもありますが、ビジネス文書では一般的に数字を半角に統一して書くことが多いです。
半角数字:1,2,3,4,5,6
全角数字:1,2,3,4,5,6
半角英字:a,b,c,d,e
全角英字:a,b,c,d,e
いずれにしても、半角と全角がバラバラなのはダメです。
事前にクライアントに確認して、どちらに統一すべきか聞いておきましょう。
カッコは全角にする
英数字は半角にした方が綺麗になる一方で、カッコは全角の方が綺麗です。(と思っています)
半角カッコ:(リアルな体験談です)
全角カッコ:(リアルな体験談です)
心配な場合は、事前にクライアントに確認して、どちらに統一すべきか聞いておきましょう。
冗長的な表現を簡潔な表現にする
冗長的な表現は簡潔な表現に置き換えましょう。
以下のような例があります。
- 「という」を極力なくす。(執筆後にF4で「という」を検索をして、可能な限り削除する)
- 「としては」や「については」を「は」に置き換える
- 使用可能です ⇒ できます
- 利用することができます ⇒ 利用できます
私もドラフトの段階で「という」を多用する傾向があるので、校正するときに「という」をF4で検索して削除しています。
強調表現の適用箇所を控えめにする
強調表現とは、太字とかマーカーのことです。
太字で表現する
マーカーで表現する
太字やマーカーの箇所が多くなると、結局何が重要なのかわからなくなりますし、チラチラして見にくくなります。
文章全体に適用せずに、文節くらいに適用するのがほどよい加減です。
(例)Webライティングを独学で学ぶときに最も効果的なのが、自分でブログを立ち上げてアウトプットすることです。
指示代名詞を極力なくす
指示代名詞とは、「これ」「それ」「あれ」「どれ」など、何かを指すときに使う代名詞のことです。
「こそあど」言葉ともいいます。
文脈上やむを得ない場合を除いて、「これ」「それ」などは、固有名詞に置き換える方がよいでしょう。
PREPで書く
PREPとは、Point 、 Reason、 Example、Pointの略です。
- Point = ポイント・結論
- Reason = 理由
- Example = 具体例
- Point = ポイント・結論(繰り返し)
1つのテーマに対して、PREPの構成にしたがって書くと、文章がとても読みやすくなります。
英語圏の大学や大学入試で書かれるエッセイでも、PREPが基本的なスタイルとして用いられています。
主語と述語の関係性を明確にする
主語と述語の関係性がぐちゃぐちゃになっている文章は、とてもわかりづらくなります。
(例)ブログには学びをアウトプットしながら学習できる特徴があるので、積極的におすすめしています。
これは前半はブログが主語になっていますが、後半の主語はブログではありません。
したがって、以下のように書き換えるとよいでしょう。
(例)ブログには学びをアウトプットしながら学習できる特徴があるので、私は積極的におすすめしています。
主語と述語の関係では、受動態か能動態かも注意が必要です。
(例)報告書には、「ブログでの収益化を目指す」と書いています。 ⇒ 報告書には、「ブログでの収益化を目指す」と書かれています。
「こと」や「とき」などは平仮名で書く
「こと」や「とき」は、平仮名で書いた方が全体のバランスがよくなります。
「いる」や「ほしい」なども同様です。
- 彼がやった時 ⇒ 彼がやったとき
- 彼がやった事 ⇒ 彼がやったこと
- 彼がやって居る ⇒ 彼がやっている
- 彼がやって欲しい ⇒ 彼がやってほしい
漢字と平仮名のバランスに注意する
文章に漢字が多くなるととても読みにくくります。
漢字と平仮名の割合は30:70がよいとされているので、校正のときに「漢字が多いな」と思ったら、漢字を平仮名に変えるか、平仮名で表現できる別の言葉にしましょう。
副詞は形容詞の直前に置く
形容詞を強調したり、補足したりする副詞は形容詞の直前に置くようにします。
(例)とてもブログは有効な方法です ⇒ ブログはとても有効な方法です
1文を短く区切る
1文が長くなると読みにくくなるので、短く区切るようにします。
1文の長さの目安は、読点「、」を2つか3つに程度おさえること、40~60文字くらいです。
数字(特に金額)にはカンマを入れる
数字は千円刻みでカンマを入れます。
カンマを入れることで、数字の桁数を瞬時に理解できるようになるからです。
以下の数字は、カンマがないと桁数がわかりませんが、カンマを入れることで「百万円」であると瞬時に認識できるようになります。
(例)1000000円 ⇒ 1,000,000円
語尾を適度に変える
同じ語尾が続くと幼稚に見えるので、適度に変えるようにします。
たとえば、「です」「しました」「ます」などは続く傾向にあるので、要注意です。
3回以上続くなら、語尾を変えることを検討しましょう。
伝聞表現をなくす
伝聞表現とは、「のようです」「だそうです」「と聞きました」など、人から聞いた話に対して使われる表現です。
伝聞表現を使うと主張が弱くなるので、読者からの信頼性を失う要因になります。
可能な限り、事実として言い切れる表現にしましょう。
(例)××だそうです ⇒ 専門家の●●さんが書いた著書「**」では、××と主張しています
参考にした情報の元を明らかにする
外部の情報を参考にして記事を書いた場合は、参考にした情報の元(URLや本のタイトル・ページ数など)を明らかにしましょう。
参考元の情報にアクセスできるようにしておくと、発注者が「コピーコンテンツでないか」、「引用元を明確にするべきか」などを容易に判断できるからです。
わざわざ情報元を添付してくる人は、コピペで文章を書いてくることはまずないと考えられるので、発注者を安心させるという意味でもおすすめです。
文章以外のルール
文章以外のルールは、あくまで私が外注先に言っているものなので、必ずしも一般的な内容ではないかもしれません。
ご参考までに載せておきます。
画像の代替テキストをつける
Googleは画像の内容を理解できないので、SEO対策として画像に代替テキスト(alt属性)をつけます。
たとえば、ユーザー登録の手順を表す画像であれば、「●●(サービス名)のトップページ」「●●のユーザー登録画面」「●●のクレジットカード情報入力画面」などを代替テキストとして書いておきます。
こうすることで、Googleが画像の内容をより正確に認識してくれるので、SEOでも有利に働きます。
ファイル名は半角英数字、英語には小文字、空欄にはハイフンを使う
画像などのファイル名には、半角英数字を使います。
英語には小文字をだけを使用します。
空欄(スペース)は何文字分の空欄が入っているかが見てわからないので、空欄のかわりにハイフンでつなぎます。
(例)Blog manual.jpg ⇒ blog-manual.jpg
文章を校正するときのポイント
文章を校正するときは、以下2つを必ず実施します。
この2つを仕上げとして実施するだけで、記事の品質が劇的に高まります。
印刷して赤ペンチェックをする
書き上げた文章を印刷して、自分で赤ペンで修正しながら誤字脱字や不自然な言い回しなどをチェックします。



赤ペンチェックをすることで、誤字脱字をほぼゼロにできます。
誤字脱字がある状態で納品すると、「この人はちゃんと校正していないな」と信頼を失う原因になるので、手間はかかりますが必ず赤ペンを入れてチェックするようにしましょう。
声に出して読む
書いた文章を声に出して読みます。



声に出して読むことで、リズムの悪いところ、冗長的な表現、同じ語尾が続く箇所などを容易に見つけられます。
3,000文字の記事だと、読み上げるのに10分くらいかかりますが、それだけの時間をかける価値のある作業です。
自動校正ソフトを使う
自動校正ソフトを使って文章の質を高める方法もあります。
私が使っているのは「文賢(ぶんけん)」というクラウドサービスです。
文賢には、表現の修正、校閲、推敲などを自動で行う機能のほか、読み上げ機能もついています。



ソフトが自動判定してくれるので、文章チェックの手間を大幅に削減できています。
「沈黙のWebライティング」の著書で有名な松尾氏が運営している会社が販売しています。
文賢の公式サイト⇒ https://rider-store.jp/bun-ken/
まとめ
私が外注向けに運用しているマニュアルの中で、ライティングのコツとして活用できる内容を抜粋しました。
Webライターは顔を見せて仕事をすることが少ないので、納品した記事の内容だけで良し悪しを判断されてしまいます。
明らかにセルフチェックが不十分と思われる記事を納品してしまうと、それだけで「次に発注することはないな」と思われてしまいます。
記事を納品する前には、最低限のセルフチェックをして、少しでも記事の品質を高めて納品することを癖にしていきましょう。